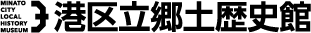麻布本村町会 麻布氷川神社祭礼関連資料
- 所在地
- 南麻布3-3-36
- 所有者
- 麻布本村町会
- 概要
- 17点 有形民俗文化財 令和6年10月17日指定
麻布本村町会が所有する、麻布氷川神社の祭礼に関連する資料類です。江戸後期から昭和初期にかけての資料で、氏子町である麻布本村町(里俗の地名は上ノ町と新町)で用いられた山車人形 2体(素戔嗚命・武内宿祢)、高欄 2基、飾り幕 2枚、木造獅子頭 1対、扁額 2面、祭礼行列図扁額 1面、等からなります。
江戸時代、麻布氷川神社では山車を仕立てた巡行行列が数年~数十年の中絶期間を経て断続的に行われました。幕府の支援を受けて行われた山王祭、神田祭とは異なり、氏子町の資金力に依拠し、一定の祭礼資金が見込める時期に行われたものと考えられています。
近代以降、祭礼で人形山車が曳かれる機会は減り、山車人形は神酒所に飾られるようになります。麻布本村町会会館でも毎年9月の祭礼の時期に神酒所を設け、山車人形や獅子頭を中心とした祭礼飾りを行っています。山車人形の素朴なつくりは地域的特色を反映しており、後世の修理を経ながらも当初の姿をとどめています。付属する飾り幕や扁額には年代や奉納者が記されています。また雌雄の獅子頭は丁寧で力強い造作で、頭上に彫られた銘(「彫工 後藤三四郎 橘恒俊」)により関東彫工の一派による作品であることが分かります。また昭和10(1935)年の祭礼行列図からは、人形山車中心の祭礼から神輿中心の祭礼へと移行する様子や、獅子頭山車の巡行など、昭和初期の様子を知ることができます。
これらの資料は江戸時代から近現代にいたる祭礼の変遷を示すものであり、麻布地域の信仰や民俗を知る上でも重要です。麻布氷川神社の氏子町である麻布本村町内に今日まで大切に伝えられ、現在も祭礼で使用されている点においても貴重な文化財といえます。